部下を見ていて
「今の仕事に向いていないかもしれない」
「部下が育たない」
と感じる場面は、どの職場にもあります。
注意して見ているつもりでも成果が上がらず、周りのメンバーとのギャップも広がっていくと、管理職として心がざわついてきます。
その一方で
「本当に適性がないのか」
「どう対応していけばいいのか」
と迷いが生まれやすいのも、このテーマの難しいところです。
あわてて
「部下は、このが仕事向いてない」
「部下に適性がない」
と決めつけてしまうと、後から振り返って「もう少し別の対応もあったかもしれない」と感じる可能性もあります。
職場の研究では、仕事と人の相性(パーソン・ジョブ・フィット)が高いほど、仕事への満足感やパフォーマンスが高まりやすいことが示されています。psychologie.uni-mannheim.de+1
一方で、その相性が低い場合でも、上司の支え方や職場の環境によって、業績や定着が改善することも分かってきています。
この記事では、「部下に適性がない」と感じた時に、上司が取るべき対応の全体像と、すぐに結論に飛びつかずに試していける対応策をまとめます。
▶ 部下の指導 タイプ別|なぜ人によって伝わり方が違うのか(基礎編)
仕事に向いていないように見える理由は「適性」と「環境」が重なっていることが多い
部下が伸びない理由を考える時
-
能力や性格などの「適性」の問題
-
仕事の量や教え方など「環境」の問題
を切り分けて見ることが大切です。
「人と仕事の相性」と「人と会社の相性」は、満足度や成果と関係があるといわれています。エメラルド+1
ただし、これは「合わないから終わり」という意味ではなく「どこを整えれば力が出やすいか」を考えるヒントになります。
| 視点 | 例 | 誤解しやすいポイント |
|---|---|---|
| 適性(向き・不向き) | 数字が得意 / お客様対応が得意 など | 一時的なつまずきも「適性がない」と決めつけてしまいやすい |
| 環境(周りの条件) | 業務量が多い / OJTが不足 / チームの雰囲気が緊張しすぎている | 環境の影響なのに、本人の性格や能力のせいにしてしまいやすい |
たとえば、Googleが社内チームを詳しく調べた「プロジェクト・アリストテレス」という研究では、安心して意見を出せるチームほど、パフォーマンスや創造性が高くなることが分かっています。
これは、部下の力が出るかどうかが、本人の努力だけでなく、チームの雰囲気や上司の対応にも左右されるということを示しています。
部下が伸びない理由を考える時は、本人の適性のあるなしだけでなく
・今の仕事の設計
・周囲の支え方
・チームの空気
といった環境も一緒に見ていくことがポイントになります。
部下の適性がないと判断する前に確認すべきこと
ここからは、現実の職場で試しやすい形に落とし込んだ7つの対応策です。
すべてを一度に行う必要はありません。今の状況に合いそうなものから、小さく取り入れていくイメージで読んでもらえるとちょうどいいと思います。

① 事実を書き出して「感じていること」と分けて整理する
最初におすすめしたいのは、感情ではなく事実を紙に書き出すことです。
「何となく適性がない気がする」という状態から一歩進めるために、次のような点を箇条書きにします。
-
どんな場面でうまくいかないのか
-
逆に、比較的スムーズにできている業務は何か
-
周囲のメンバーとの違いはどこか
この作業をすることで、「全部ダメ」に見えていた部下にも、できている部分と、つまずきやすい部分が分かれていることが見えてきます。
② 本人の言葉をていねいに聞く時間をつくる
次に、本人がどう感じているかを落ち着いて聞く対話の時間をとります。
上司からの一方通行のフィードバックだけでは、本当のつまずきが見えにくくなります。
たとえば次のような、答えやすい質問から始めると話が出てきやすくなります。
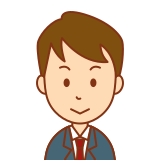
「やりやすいと感じる仕事はどの部分ですか」
「最近いちばん負担に感じている場面はどこですか」
重要なのは、評価の場ではなく、状況を一緒に整理する場です、と最初に伝えることです。
部下とのコミュニケーションの基本を整理したい時は、こちらの記事も役に立ちます。
▶ 部下とのコミュニケーションが難しい時の解決策
③ 業務量・難易度・サポート体制を見直す
部下が育たないと感じる時、業務量や難易度が、その人の今の状態に対して高すぎるケースも少なくありません。
上司からのフィードバックやOJT(職場での実地指導)の不足も、パフォーマンス低下と関係があるとする研究があります。IJISRT+1
-
この人だけ業務が偏っていないか
-
教える人が固定されていて、説明の仕方が合っていないのではないか
-
締め切りや優先順位が曖昧になっていないか
といった視点で、「この条件であれば、自分でも大変ではないか」と一度フラットに見直してみることが大切です。
④ 小さな成功体験を意図的に積ませる
ハーバード・ビジネス・スクールの研究では、「少しずつ進んでいるという感覚(小さな達成)」が、仕事の意欲や創造性を高めることが示されています。Creativity at Work+2ハーバードビジネスレビュー+2
この「進捗の原則」に合わせて、次のような工夫をします。
-
難しい仕事を、もう一段細かいステップに分ける
-
時間内に終えやすいタスクを任せて「できた」を増やす
-
終わった仕事に対して、具体的な良い点をフィードバックする
「できたこと」が見えるようになると、部下の表情や声のトーンが少し変わってくるはずです。
⑤ 強みや得意な場面を一緒に探す
人によって、力を発揮しやすい場面は大きく違います。
数字を扱うほうが楽な人もいれば、お客様と話すほうが自然に動ける人もいます。
事実の書き出しや対話の中で
-
他の人よりも早く終わらせられる仕事
-
苦にならずに続けられている作業
などを確認し、「この部分は強みかもしれませんね」と言葉にして返すことが、本人の自覚と自信につながります。
⑥ 成長のペースと評価のタイミングを調整する
評価のタイミングが短すぎると、「まだ形になっていない途中経過」で判断してしまいがちです。
一方で、結果を先送りにしすぎると、部下も上司も不安が高まります。
たとえば
-
1〜2か月ごとに小さな到達点を決める
-
その都度、「できたこと」「改善点」「次の一歩」を確認する
といった形で「長距離走のラップタイム」を一緒に見ていくイメージを持つと、双方の負担が軽くなります。
⑦ 配置転換や役割変更を、自然な選択肢の一つとして検討する
それでも「今の仕事と相性が良くない」と感じる場合は、配置転換や役割の変更も、選択肢の一つになります。
ここでも、いきなり結論を提示するのではなく、本人の希望や強み、職場全体のバランスをていねいに確認していくことが大切です。
配置の話も、追い詰めるためではなく、力を出しやすい場所を一緒に探すためというスタンスで向き合うことで、受け止められ方が変わります。
小さな変化のサインを見逃さない
上記のような対応策を続けていくと、劇的な変化ではなくても、少しずつ変化のサインが出てきます。
-
報告や相談の頻度が少し増える
-
同じミスが続かなくなる
-
できたことを自分から話してくれる
こうした小さな変化は、「今の方向性で合っている」という一つの証拠になります。
逆に、このサインがまったく見られない場合は、環境や役割の見直しを、もう一段踏み込んで考えるタイミングかもしれません。
▶ 指導が響かない部下:反応が薄い・動かないタイプの特徴と向き合い方
すぐに「適性がない」と決めつけず、7つの視点でじっくり確認
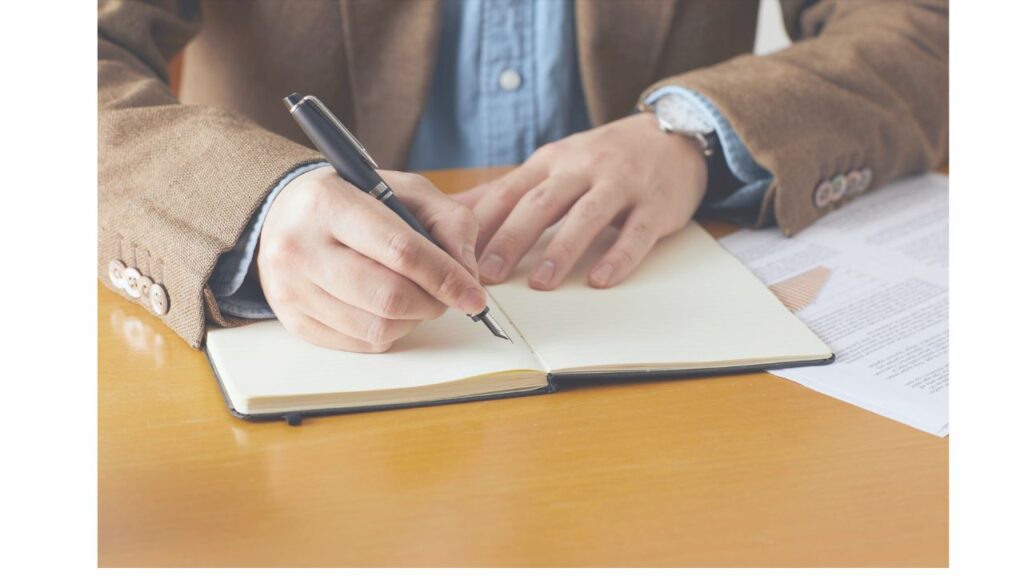
部下が今の仕事に向いていないと感じる時、管理職の心には迷いとプレッシャーが同時にのしかかります。
ただ、研究や実務の知見を合わせてみると、「人と仕事の相性」と「職場の環境」の両方を見ていくことが、納得感のある判断につながることが分かってきています。psychologie.uni-mannheim.de+2エメラルド+2
この記事で紹介した7つの対応策は、どれも特別なツールを使わず、今日から少しずつ試せる内容です。
-
事実を書き出して整理する
-
本人の言葉をていねいに聞く
-
業務量・難易度・サポートを見直す
-
小さな成功体験を積ませる
-
強みや得意な場面を一緒に探す
-
成長のペースと評価のタイミングを調整する
-
配置転換や役割変更を自然な選択肢として検討する
どれか一つだけでも、職場の空気や自分の気持ちが、少し軽くなるはずです。
「部下が、この仕事に向いてない」と感じる瞬間こそ、判断を急がず、状況と環境の両方を整えていく。その積み重ねが、チーム全体の安定にもつながっていきます。
関連記事:
▶ 【上司の自己診断チェックリスト】部下から好かれる中間管理職の共通点
▶ 中間管理職のストレスは人間関係の「割り切り」で激減する
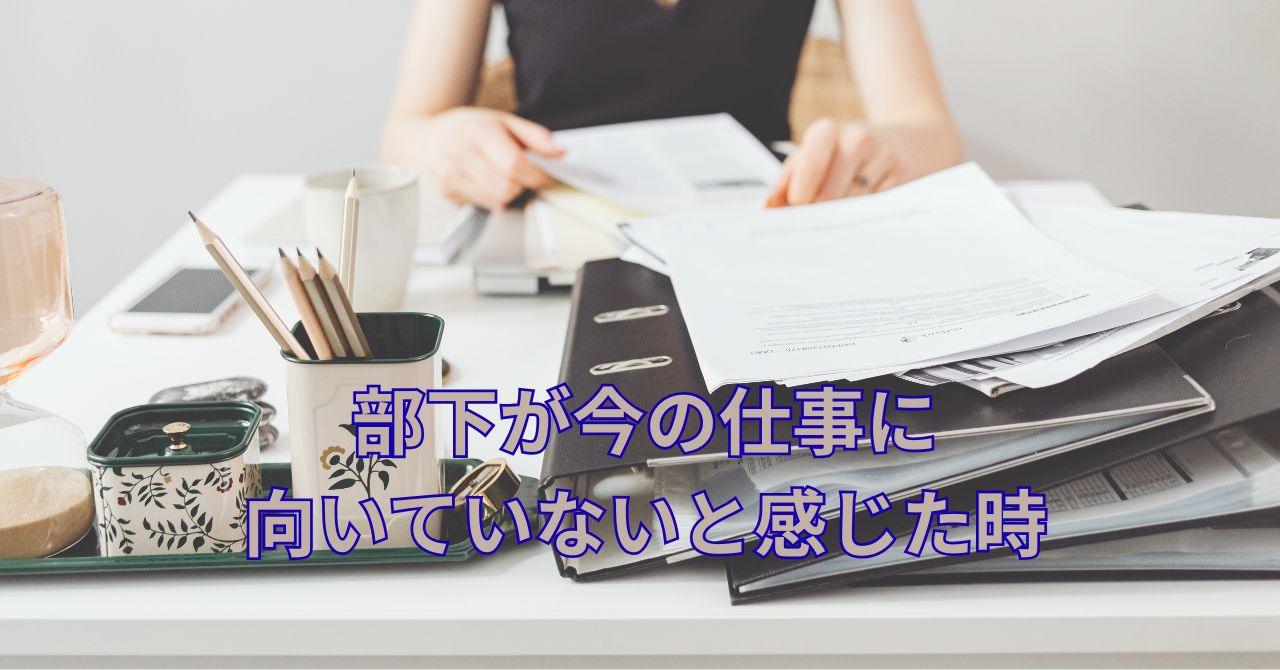


コメント