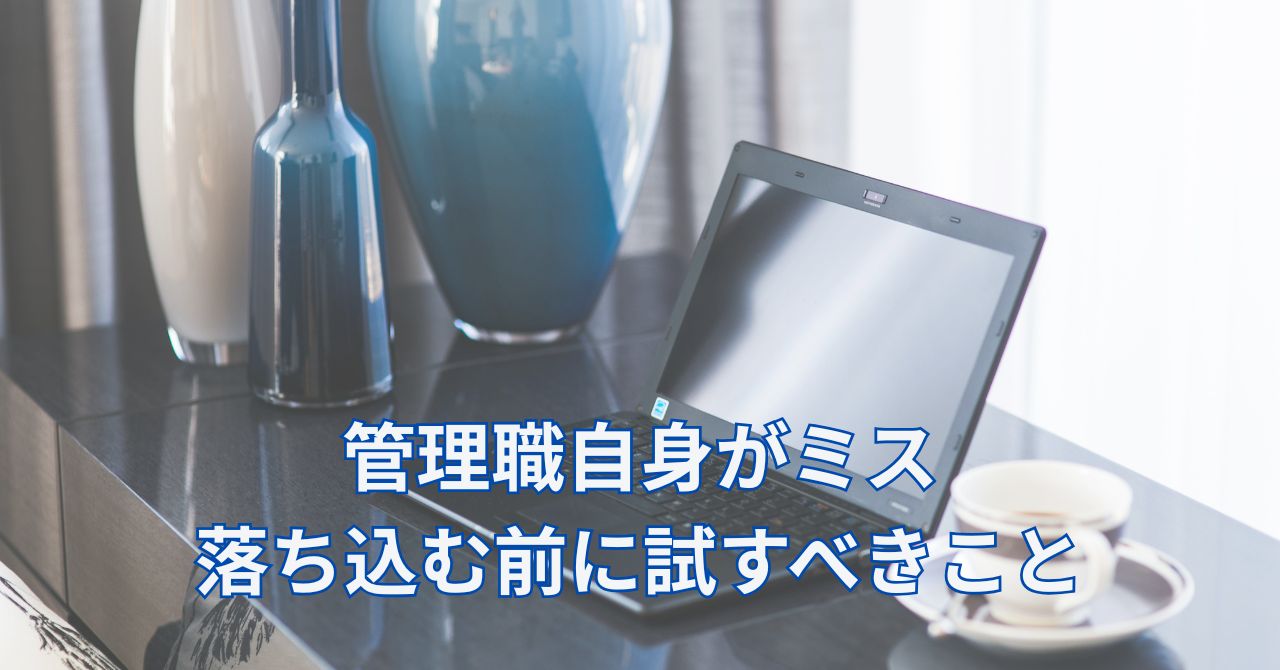仕事を続けていると、ミスが重なって気持ちが沈んでしまう日もあります。特に、管理職という立場なら、なおさら負担が大きくなり、深く落ち込むこともあるでしょう。この記事では、管理職がミスで落ち込む状況から抜け出すための視点を整理しました。
▶ 【上司の自己診断チェックリスト】部下から嫌われる中間管理職の共通点
なぜ管理職はミスで深く落ち込むのか?責任感の正体

管理職は判断の場面が多く、緊張が続きやすい立場です。
状況が変わると、慣れない環境に気持ちが追いつかず、ミスが起きることがあります。
筆者も環境が変わった直後は、普段ならしないようなミスを重ねて、落ち込んだ時期がありました。仕事の流れをつかめず、もう立ち直れないと感じた日もあります。それでも、周囲の支えがあり、少しずつ回復できました。
ミスは能力ではなく、環境と心の状態にも左右されます。
落ち込む前に知っておきたい3つの事実
ミスの背景には、忙しさや情報量の増加など、環境要因が関係していることが多いです。
見えにくい成果が多い管理職は、できていることに気づきにくい特徴があります。
筆者も異動後に、業務が自分に合っていると実感でき、以前より落ち着いて判断できるようになりました。
この経験から、ミスは自分を責める材料ではなく、状況を整えるサインだと考えるようになりました。
落ち込みやすい時期があるのは自然なことです。
視点1〜3:ミスばかりに見える状況を整理する
視点1:ミスの種類を分ける
起きたミスは「思い込みによるもの」「情報の行き違い」「業務量の増加」のように、種類で分けます。種類を分けると、改善の方向が見えやすくなります。
視点2:状況のパターンを見る
どの場面でミスが増えるのかを振り返ると、傾向がつかめます。朝の時間帯なのか、人が多い場面なのか、作業が重なった時なのか。
パターンが分かるだけで、対処しやすくなります。
視点3:役割の見方を変える
「ミスをした管理職」と捉えると、気持ちが疲れやすくなります。
「改善を進める役割」と捉えると、視線が前に向きます。
筆者も当時は自分を責めていましたが、視点を変えることで気持ちが軽くなりました。
視点4〜5:ミスが多い管理職にならないための仕組みづくり

視点4:減らしたいミスを1つに絞る
チェックリストを増やすほど負担が増えます。
減らしたいミスを1つに絞ると実行しやすくなり、効果も出やすくなります。
例えば、メールの宛先ミスなら『送信前に10秒、声出し確認をする』という1点だけに集中する。これだけで脳のスイッチが切り替わります
視点5:共有で負担を減らす
管理職がミスを抱え込むと、視野が狭くなります。
部下と「気になった点」を共有すると、何が起きているのか見えやすくなります。
言いやすい空気を作るために、以下のような質問が役立ちます。
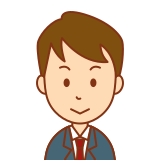
「やりづらさを感じた場面はありましたか」
「流れで気になるところはありますか」
少しずつ共有が広がると、改善が進みます。
視点6〜7:落ち込む心を整える習慣
視点6:できたことを書き出す
1日の終わりに、できたことを3つ書く習慣は、気持ちの整理に向いています。
大きな成果でなくても大丈夫です。落ち込みやすい時期ほど効果があります。
視点7:長い視点で今を見る
短期間で判断すると、自信をなくしやすくなります。
筆者も、環境が合ったことで本来の力を取り戻すことができました。この経験から、状況に合わせて力が発揮される時期があるとわかりました。
長い視点を持つほど心が整いやすくなります。
参考:厚生労働省 こころの耳:ストレスと上手につきあおう(外部リンク)
ミスが続く管理職こそ意識したい、周囲とのコミュニケーション
ミスを一人で背負うと、心が疲れてしまいます。
部下の前では線引きをし、必要以上に落ち込まないように気持ちを整えることも大切です。
「一緒に流れを整えていきたい」と伝えると、改善が前向きに進みます。
ミスを経験した管理職は、ミスをした部下の気持ちがわかるようになります。
この視点は、職場づくりに大きなプラスになっていきます。
まとめ:ミスで落ち込む日にも役立つ視点を持つ
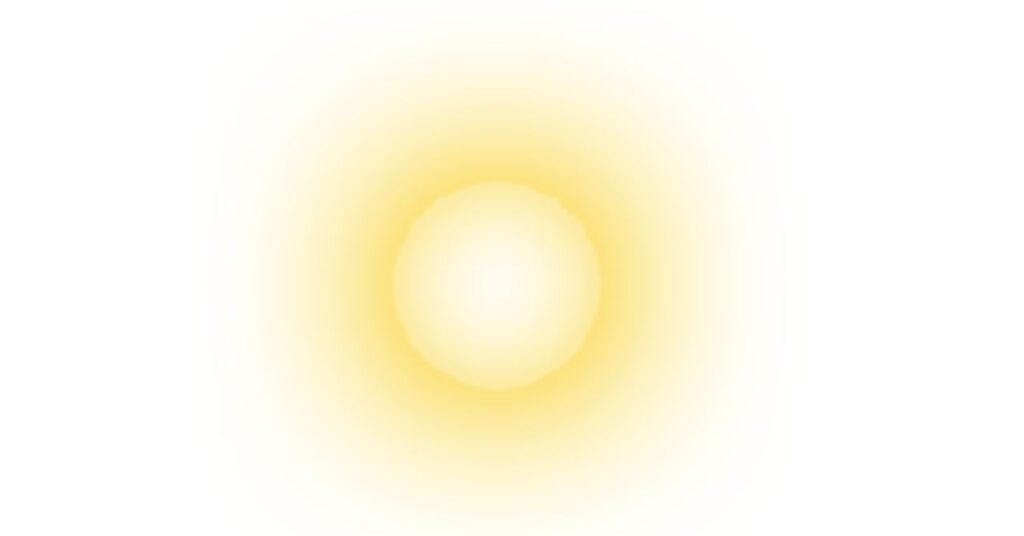
ミスは、決して能力の否定ではありません。
状況が変われば、力の発揮され方も変わります。
できない部分だけで判断せず、全体を見ながら視点を整えることが、穏やかな働き方につながります。