それなのに在宅ワークが当たり前になり、「通勤がない分ラクになったはず」と思っていたのに、なぜか心が重い。特に中間管理職として、部下のマネジメントと上司への報告に挟まれ、オンラインだからこそ気を使う毎日ではありませんか?
私も中間管理職として、在宅勤務が始まった当初は「満員電車から解放された!」と喜んでいました。ところが1か月後には、体は疲れていないのに心だけがずっしり重い日々が続いたのです。
この記事では、私自身が中間管理職として経験した在宅ワーク疲れの正体と、実際に効果があった対策をお伝えします。マネジメントの工夫だけでなく、制度活用やセルフケアの視点も含めて解説するので、今日からすぐ実践できる内容です。
- 中間管理職が在宅で疲れる科学的な理由
- オン・オフを切り替える具体的な環境づくり
- 部下と上司双方との信頼を保つコミュニケーション術
- 管理職としてのキャリア停滞を打破する行動指針
中間管理職が在宅ワークで逆に疲れる3つの理由

| 働き方 | メリット | デメリット | 補足 |
|---|---|---|---|
| 在宅勤務 | 通勤負担ゼロ | 孤立感が増える | 境界線の工夫必須 |
| 出社勤務 | 社内コミュニケーションしやすい | 移動疲れあり | リフレッシュには有効 |
【体験談】通勤がなくなったのに心が重くなった管理職の1か月
在宅勤務が始まった最初の1週間は、正直最高でした。
朝の満員電車がない。身支度も最小限。通勤時間が浮いた分、朝の時間に余裕ができる。
それなのに2週間目に入ると「ずっと家にいるのに休んだ気がしない」という違和感が芽生え始めました。
そして1か月後には、部下からのチャットが気になり、上司への報告タイミングに悩み、誰とも直接話していないのに妙に気疲れする日々。朝起きてすぐパソコンを開き、昼食も適当にすませ、気づけば夕方。仕事部屋から一歩も出ずに、1日が終わる生活が続いていたのです。
通勤がなくなったぶん、体はラクなはずなのに、心の重さを感じる。特に管理職としての責任が、オンラインでは見えない形で肩にのしかかっていました。
原因①:生活と仕事の境界があいまいになる
在宅ワーク最大の課題は、生活空間と仕事空間が混在することです。
総務省の調査では、「テレワーク・在宅勤務において仕事とプライベートの切り替えが難しい」と感じている人が一定割合に上るという結果が示されています。
特に管理職の場合、部下からの相談や緊急対応が夜間や休日にも入ることがあります。
物理的に同じ空間で生活と仕事を続けると、脳が「休息モード」に切り替わりにくくなります。
通勤という移動時間が、実は気持ちの切り替えスイッチとして機能していたことに、私は在宅勤務を始めて初めて気づきました。
▶ 在宅ワークで体がなまる?肩こりと運動不足を防ぐ簡単な習慣
原因②:過集中と板挟みによる心の負担
オフィスにいれば、同僚の話し声や会議の時間で、自然と区切りがつきます。
でも在宅では、誰にも邪魔されない環境だからこそ、気づかないうちに過集中状態が続いてしまいます。さらに管理職特有の悩みとして、部下の相談対応と上司への報告作成を、同時並行で進めるプレッシャーがあります。
休憩を取らずに3時間も4時間もパソコンに向かい続け、ふと我に返ったときには、心身ともにぐったり。この「自分で区切りをつける力」と「優先順位をつける判断力」の両方が求められるのが、管理職の在宅ワークの難しさです。
原因③:見えないストレスの蓄積
在宅勤務では、対面では伝わっていた微妙なニュアンスが伝わりません。
特に管理職として気になるのは、以下のような不安です。
- 「部下のモチベーション、ちゃんと把握できているかな?」
- 「上司にこの言い方、失礼に思われないかな?」
- 「チームの雰囲気、悪くなっていないだろうか?」
こうした目に見えない気遣いが、じわじわと心を削っていきます。そして通勤で自然に発散できていたエネルギーの循環が、在宅では意図的に作らないと失われてしまうのです。
管理職が疲れをためこまない環境づくり5つの習慣
①仕事と生活を物理的に分ける
まずは「空間の分離」から始めましょう。
部屋が一つしかなくても大丈夫です。私が実践したのは以下の工夫です。
- 座る椅子を「仕事用」と「食事・リラックス用」で分ける
- 部屋着と仕事着を明確に分ける(在宅でもビジネスカジュアルに着替える)
- デスク周りに、仕事に関係ないものを置かない
特に効果的だったのが、終業後に必ず5分の散歩に出ること。ただ外の空気を吸うだけで、驚くほど気持ちが切り替わります。
管理職として「いつでも対応できる状態」を保つより、「しっかり休んで明日に備える」ほうが結果的にチームのためになります。
②「終業の儀式」を作る
在宅勤務では、終業のタイミングが曖昧になりがちです。
私が取り入れたのは「終業の儀式」です。
- 17時30分にタイマーをセット
- お気に入りの音楽をかける
- 部屋の窓を開けて空気を入れ替える
- パソコンを閉じる
この一連の流れを毎日繰り返すことで、脳が「仕事終わり」を認識するようになりました。儀式は何でも構いません。自分にとって心地よい「区切り」を作ることが大切です。
部下にも「18時以降の連絡は翌朝対応」とルールを伝えることで、お互いの時間を尊重する文化が生まれました。
③休憩時間を義務化する
過集中を防ぐには、休憩を義務化することが有効です。
休憩中は必ず席を立ち、軽いストレッチや白湯を飲むなど、意識的に体を動かします。これだけで午後の集中力が格段に上がり、部下への対応や上司への報告の質も向上しました。
④制度活用:フレックスや時短を検討する
もし会社に、フレックス制度や時短勤務制度があるなら、管理職でも積極的に活用を検討しましょう。
特に介護や子育て中の方は、無理をせず制度を活用することで、長期的にチームに貢献できます。
私が先輩管理職に聞いた言葉が印象的でした。「制度を使わずに体調を崩すほうが、周りに迷惑をかける」。この視点を持つことで、罪悪感なく制度を活用できるようになります。
⑤やらないことリストを作る
在宅ワークでは、つい「あれもこれも」と手を広げがちです。
そこで私が作ったのが「やらないことリスト」
| やらないこと | 理由 |
|---|---|
| 昼休み中のメールチェック | 休息時間を死守するため |
| 18時以降の新規タスク着手 | 終業時間を明確にするため |
| 全ての通知をオンにする | 集中を妨げないため |
| 部下の業務を全て把握しようとする | 信頼と自律を促すため |
「やること」ばかりに目が行きがちですが、「やらないこと」を決めるほうが、心の余裕を保てます。管理職だからこそ、全てを抱え込まない勇気が必要です。
オンラインでも部下・上司と信頼を保つコミュニケーション術
![]()
1日1回、自分から声をかける
在宅勤務が続くと、仕事の相談も雑談も減ります。これが孤立感につながり、心の負担を加速させます。
私も「部下の本音が見えない」「上司に評価されているか不安」と悩んだ時期がありました。でも、勇気を出して1日1回だけでも「お疲れさまです、今日の作業どうですか?」とチャットを送っただけで、気持ちが一気にほぐれたのです。
距離を感じるほど、意識して声をかけ合うことが大切です。特に管理職から声をかけることで、チーム全体の心理的安全性が高まります。
「頼りながら自立する」バランス感覚
孤立を恐れるあまり、何でも自分で抱え込む必要はありません。
まず管理職としても、以下の3つの工夫を意識してみてください。
- 相談グループを作る:同じ立場の管理職と定期的に話す場を設ける
- 「申し訳ございません」を減らす:謝る代わりに「ありがとうございます」で伝える
- 相手の状況を決めつけず聞く:「今、相談してもよろしいでしょうか?」と確認する
「助けが必要なときには頼る。でも、自分の足でも立てる構えを持つ」このバランス感覚が、メンタルを安定させるポイントです。管理職も完璧である必要はありません。
管理職のキャリア停滞感を打破する3つの行動
成果の「見える化」を習慣にする
オンライン環境では、貢献が目に見えにくいため、評価されにくいと感じてしまいます。
そこで大切なのが、成果を「結果」だけでなく「経過共有ベース」で見せることです。
例えば、こんな報告を週1回送るだけで印象が変わります。
- 「今週はチームでA案件を進めています。部下のBさんが主導し、順調です」
- 「C業務で少し課題が出ていますが、D方法を試してみます」
小さな段階でも報告することで、上司への信頼構築と、自分の存在感を自然と示せます。また部下の成果を積極的に報告することで、チームの評価も上がります。
在宅時間を自己投資時間に変える
通勤時間がなくなった分、自己投資の時間が生まれたと考えることもできます。
だから私は通勤時間に使っていた往復2時間を、マネジメント研修やライティングの学習に充てました。
今はオンラインで学べる環境が整っています。管理職としてのスキルアップ講座や、次のキャリアに備えた資格取得など、家にいながら未来の可能性を広げられます。
セカンドキャリアも視野に入れる
40代・50代の管理職の方は、そろそろセカンドキャリアも視野に入れる時期かもしれません。
在宅ワークで感じる「このままでいいのか?」という不安は、次のステージに進むサインでもあります。
もし今の働き方に疑問を感じたら、それは変化のチャンスです。管理職経験は、独立や転職でも大きな武器になります。
よくある質問
Q1: 在宅ワークで疲れるのは甘えですか?
いいえ、甘えではありません。
厚生労働省の「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」でも、在宅勤務特有の心理的負担やメンタルヘルス対策の必要性が明記されています。環境の変化に心が追いつかないのは、ごく自然な反応です。
Q2: 在宅ワークを続けるか、出社に戻すか迷っています
どちらが正解ということはありません。
大切なのは、自分にとって心地よい働き方を選ぶことです。在宅が合わない場合は、週に数日出社する「ハイブリッド勤務」を相談するのも一つの方法です。無理に我慢せず、上司や人事に相談してみましょう。
Q3: 家族がいる中での在宅ワークがしんどいです
家族との境界線を引くことが重要です。
- 仕事中は部屋のドアを閉める(物理的境界)
- 「〇時まで仕事」と家族に共有する(時間的境界)
- ヘッドホンをつけて集中サインを出す(視覚的境界)
また、介護や育児と両立している場合は、会社の支援制度(時短勤務、介護休暇など)の活用も検討してください。管理職でも制度を使うことは可能です。
まとめ:完璧じゃなくていい。少しずつ自分を整えよう
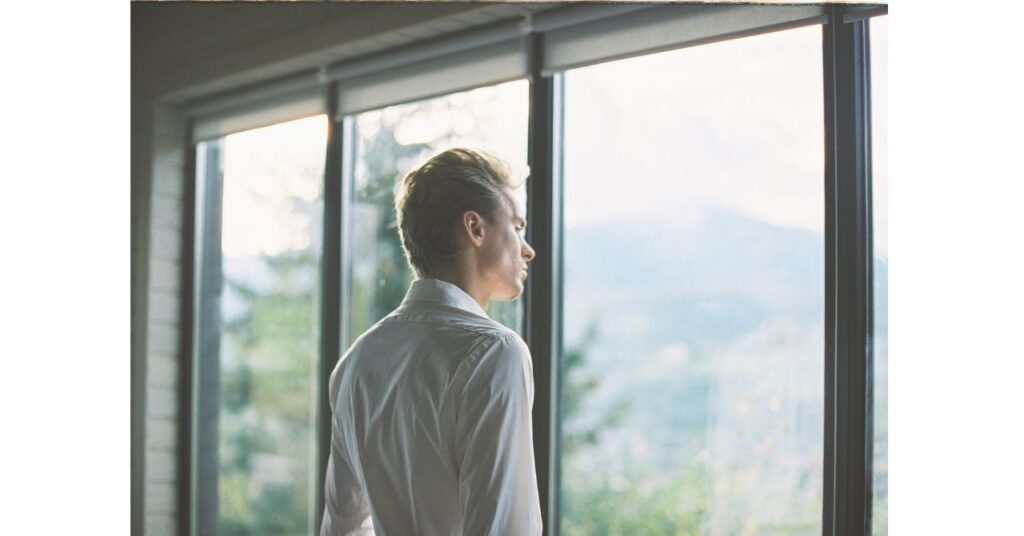
在宅ワークは、通勤疲れからは解放されます。でも、逆に疲れることもある。
それはあなたが弱いからではなく、環境が急激に変わったからです。特に中間管理職として、部下と上司の間で気を使う毎日は、想像以上に心に負担をかけています。
今日お伝えした内容をまとめます。
・環境づくりは小さな習慣から(椅子を分ける、終業の儀式など)
・孤立感を防ぐには、管理職から1日1回の声かけが効果的
・キャリアは「見える化」と「自己投資」で前に進む
今日から始められる3ステップ
- 明日から試す:終業後の5分散歩を取り入れる
- 今週中に実践:1日1回、部下や同僚に声をかけてみる
- 来月の目標:自分とチームの成果を週1回、上司に経過報告する
小さな一歩が、大きな変化につながります。
ほんの少し、習慣や工夫を足してみることで、在宅勤務はもっとラクになります。
完璧じゃなくて大丈夫です。あなたの一歩を、心から応援しています。
参考情報
総務省「令和4年通信利用動向調査」
厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」(令和3年改定)
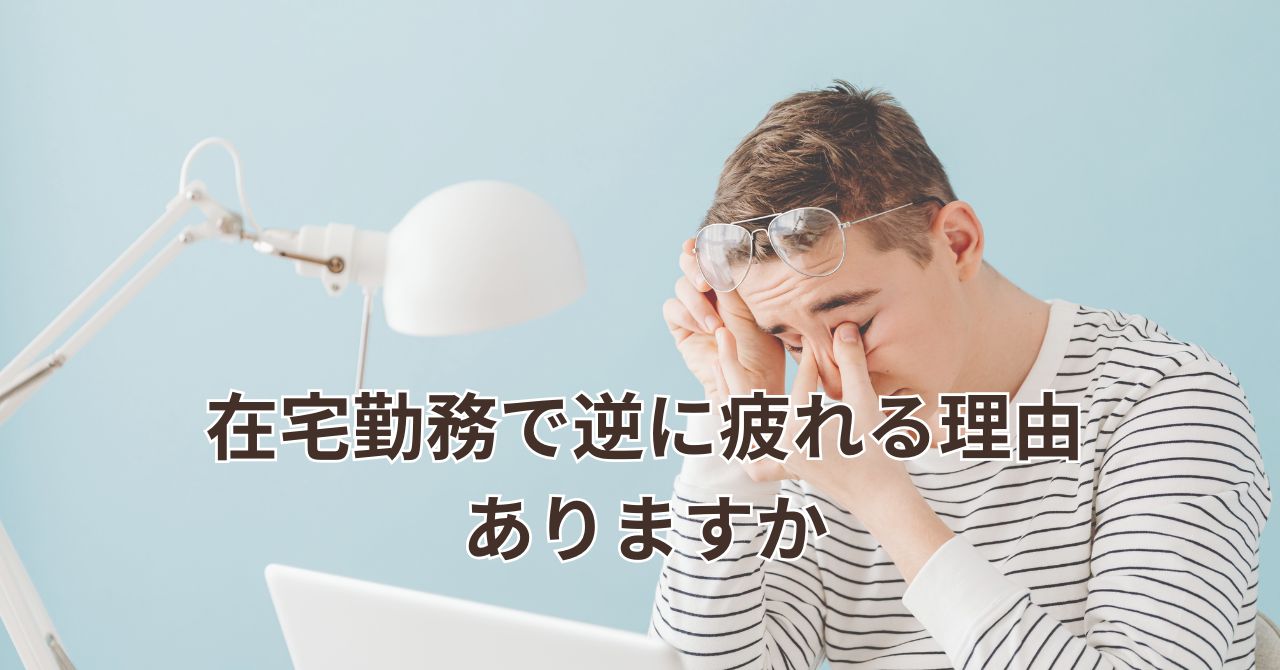


コメント