口コミの点数も、有名さも、自分に合う心療内科かどうかは教えてくれません。
私が適応障害の初期に経験したのは、10分診察で不安が残る病院と30分以上話を聞き、道筋を示してくれた病院の差。
心療内科の選び方を知らないまま受診すると、不安が増えたり、回復が遠回りになることもあります。
この体験から見えた「失敗しない選び方」を、初診の質問例・診断書の相談法・転院の判断基準まで実践手順でお届けします。
読み終わった時、なにか1つ行動できる形でまとめました。
迷っている時間を、少しでも短くしましょう。

転院までの流れを落ち着いて振り返る
最初に受診したA院
初診が10分ほどで終わりました。症状は聞いていただけたのですが、治療の進め方や働き方の相談はあまり深まりません。「このまま通って大丈夫だろうか」という不安が残りました。
家族の勧めで行ったB院
ここでは30分以上かけて、症状だけでなく仕事や家庭の状況まで、丁寧に確認がありました。結果として、当面は休む選択肢を取り、職場と調整し、小さなステップで復職を目指す道筋を示していただけました。
この違いを経験して
・医師の説明のわかりやすさ
・治療の見通しの具体さ
・一緒に進めてくれる姿勢
が、安心感に直結するのだと実感しました。
初診で良いサイン/避けたいサインを見極める

| 良いサイン | 避けたいサイン |
|---|---|
| 初診に20〜30分ほど時間を取り、生活・仕事・家族のことまで聞き取ってくれる | 診察が極端に短く、説明がぼんやりしている |
| 治療の進め方(頻度・目安・確認ポイント)や復職までの道のりを具体的に説明してくれる | 仕事や働き方の話題がほとんど出てこない |
| 通院のペースや、必要に応じた家族・産業医との連携に前向き | 診断書の相談をしても はっきりした回答が得られない |
| 必要であれば診断書の相談に応じてくれる | (特になし) |
一言メモ:回復には環境の整え直しも大切です。
医師が「治療だけ」ではなく、働き方や職場との調整まで
視野に入れてくれるかが判断のポイントになります。
受診前に伝える内容をメモにまとめる
診察を充実させるいちばん簡単な準備は短いメモです。スマホで十分です。
持っていくメモ(例)
| ここ1〜3か月の症状の流れ | 悪化・楽になったきっかけを各1行ずつまとめておく |
|---|---|
| 仕事の状況 | 残業時間の目安、配置替え、対人関係などを具体的に記録 |
| 相談したいこと | 例:診断書の必要性、勤務の調整、復職の目安など |
初診で確認したいこと(例)
- 初診はどのくらい時間を確保いただけますか?
- 今後の進め方はどのような段階で考えていますか?
- 家族や産業医と情報を共有しながら進めることは可能ですか?
- 休職や復職の判断の目安、診断書の相談はできますか?
迷ったら、厚労省「こころの耳」全国医療機関検索で(2024年から「医療情報ネット(ナビ)」に統一)自分の条件に合う院を探しましょう。 こころの耳+
医師と協力して「働き方の整え方」を一緒に考える
B院の先生は、私の話をひと通り聞いたあと、静かにこう言いました。
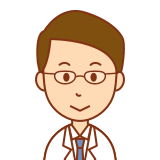
休まないとダメですよ
その一言で、張りつめていたものがほどけました。「休む=逃げる」じゃない。治すための時間が必要なんだと気づけた瞬間でした。
初診では、無理に「休みたい」と伝える必要はありません。いまの働き方が体調にどう影響しているかを、事実ベースで整理して共有することが大切です。
あなたが誠実に伝えようとする姿勢が、より良い治療方針づくりにつながります。
| 話す内容 | 伝え方の例 |
|---|---|
| 症状の変化 | 「ここ1〜2か月で、疲れやすくなったり眠れない日が増えています」 |
| 仕事の状況 | 「残業が続いていて、集中力が続かない日が多いです」 |
| 困っていること | 「業務量や人間関係のプレッシャーで体調に波が出ます」 |
| 今後どうしたいか | 「治療を進めながら、どのように働き方を整えていけばよいか相談したいです」 |
医師に伝える目的は「休むこと」ではなく、より良い働き方と回復の両立を考えるための材料を共有することです。率直な情報共有が、信頼できる治療方針につながります。
合わないと感じたらセカンドオピニオンを検討する
次のような場合は、転院を前向きに考えて大丈夫です。
-
3回通っても具体的な提案が出てこない
-
説明に納得できず自分の状況が伝わっていない感覚が続く
-
仕事や復職の話が前に進まない・診断書の相談が難航している
問い合わせの例文:

適応障害の治療と職場調整について、セカンドオピニオンを希望しています。
初診はどのくらい時間を確保いただけますか?復職の進め方や診断書の相談にも対応可能でしょうか。
明日から小さな一歩を始める
-
睡眠前の習慣を整える:就寝1時間前は画面をオフにし軽いストレッチで体を落ち着かせる
-
やらないことを1つ決める:会議を一本減らす、残業を○分までにするなど
-
支えてくれる人に順番に伝える:家族 → 上司 → 人事 → 産業医の順で診断書と調整案を共有
迷ったときは、公的な相談先(例:「こころの耳」や自治体の窓口)を最初の足がかりにすると安心です。
まとめ|完璧じゃなくて大丈夫。あなたの一歩を応援しています

🌱 復職・適応障害に関する関連記事はこちら
適応障害で休職・復職を経験した筆者が、うつなど心の不調を抱える方にも役立つよう、体験をもとにまとめています。
一歩ずつ、自分のペースで回復していきましょう。
医師の説明がわかりやすく、一緒に進めてくれる姿勢があると回復はぐっと現実的になります。
今日はメモを3行だけで大丈夫。明日は気になる病院に1本電話してみましょう。
完璧じゃなくていい。小さな一歩は、ちゃんと前に進んでいます。
参考記事:
・「適応障害の初期症状チェック」
・「休職から復職までの段階的ロードマップ」
・「働き方を整える実践チェックリスト」
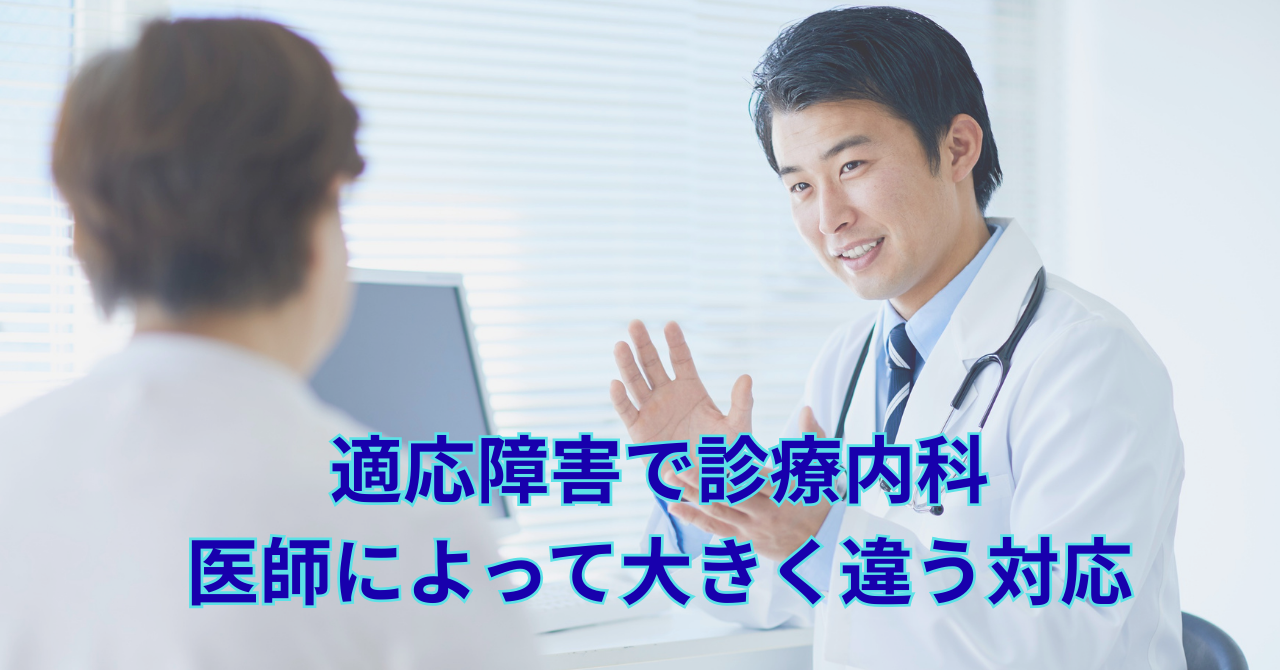
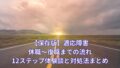
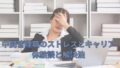
コメント