休職時の最大の不安「お金の問題」を解決する
休職を検討している時
最も大きな不安の一つが経済面ではないでしょうか。
私も、適応障害で5ヶ月間休職した際
真っ先に心配したのが、お金のことでした。
「収入がゼロになったらどうしよう」
という恐怖が、治療への第一歩を妨げていました。
しかし実際に休職してみると
適切な制度を活用することで
経済的な不安は大幅に軽減できることがわかりました。
この記事では、私の実体験をもとに
休職中に利用できる収入保障制度、申請方法
そして家計管理のコツについて詳しく解説します。
正しい知識があれば、お金の心配を最小限に抑えて
治療に専念できるようになります。
私が実際に受けた収入保障の内訳
会社からの給与保障
私の勤務先では、以下のような
手厚い制度が用意されていました。
基本的な保障内容
- 基本給の60%を継続支給
- 支給期間:最長半年間
- 社会保険料の会社負担継続
- 賞与の一部支給(在籍期間に応じて)
実際の収入例
休職前月収:35万円 → 休職中:21万円(60%)
この制度により、「当面は生活に困らない」という
安心感を得ることができました。
住宅ローンなど、固定費の多い我が家でも
何とか回せる水準でした。
利用しなかった傷病手当金
幸い、会社の制度が充実していたことと
半年以内に復職できたことで
傷病手当金は申請準備のみで
実際には利用しませんでした。
しかし、制度理解は
重要だったので詳しく調べました。
傷病手当金の基本情報
- 支給額:標準報酬日額の約67%
- 支給期間:最長1年6ヶ月
- 申請条件:医師による就労不能証明
私の場合、会社制度(60%)と傷病手当金(67%)で
それほど差がなく、会社制度の方が
手続きが簡単だったため、そちらを選択しました。
| 項目 | 会社の給与保障制度 | 傷病手当金(健康保険) |
|---|---|---|
| 支給額 | 基本給の30〜100%(会社による) | 標準報酬日額の2/3(約67%) |
| 支給期間 | 会社規定により数ヶ月〜2年 | 最長1年6ヶ月 |
| 手続き | 社内申請のみで完結 | 健康保険組合へ申請 |
| 必要書類 | 会社指定の申請書類 | 申請書、医師意見書、事業主証明 |
| メリット | 手続きが簡単、安定的 | 公的制度なので全国共通 |
| デメリット | 会社により内容が大きく異なる | 申請に時間と手間がかかる |
休職中に利用できる収入保障制度一覧
会社独自の制度
福利厚生による保障
- 給与の一部支給
(30-100%、期間は会社により異なる) - 特別休暇制度
- 社内貸付制度
- 団体保険の活用
□ 支給割合と期間 □ 社会保険料の負担割合
□ 賞与の取り扱い □ 復帰時の査定への影響
公的な収入保障制度
1. 傷病手当金(健康保険)
- 支給額:標準報酬日額の2/3
- 支給期間:最長1年6ヶ月
- 申請時期:休職開始から4日目以降
- 必要書類:医師の意見書、事業主証明書
2. 有給休暇の活用
休職前に有給休暇を消化することで
収入を満額維持できます。
- 年次有給休暇の残日数確認
- 時季指定有給の活用
- 半日・時間単位有給の戦略的使用
3. 自立支援医療制度
医療費負担を1割に軽減できる制度です。
- 通院医療費の負担軽減
- 月額上限の設定
- 申請から適用まで約1-2ヶ月
制度名 内容 支給・適用期間 ポイント 傷病手当金 標準報酬日額の2/3を支給 最長1年6ヶ月 休職4日目から申請可 有給休暇 休職前に収入を満額維持 有給残日数による 時間単位有給も活用可 自立支援医療制度 医療費負担を1割に軽減 認定から1年ごと更新 申請に1〜2ヶ月かかる 障害者手帳 長期の就労困難時に取得可能 状態に応じて交付 税制優遇や割引あり
民間保険の活用
就業不能保険
- 月額10-50万円程度の給付
- 精神疾患対応の商品も増加
- 加入前の告知義務に注意
生命保険の特約
- 入院給付金
- 通院給付金
- リビングベネフィット特約
傷病手当金申請の完全マニュアル
申請の流れと必要書類
| ステップ | 手続き内容 | 主なポイント |
|---|---|---|
| STEP1:申請書類の準備 | – 健康保険傷病手当金支給申請書 – 医師の意見書(療養担当者記入欄) – 事業主証明(事業主記入欄) |
書類は会社や健康保険組合のWebサイトで入手可能 医師と事業主の記入欄があるため 余裕をもって準備することが大切 |
| STEP2:医療機関での手続き | -主治医に意見書作成を依頼 – 就労不能期間の証明を取得 – 診療録の記載内容を確認 |
診断書ではなく「意見書」が必要 医師の記入内容が申請可否を左右するため 通院時にしっかり確認を |
| STEP3:会社への申請 | – 人事部への申請書提出 – 給与支給状況の証明取得 -出勤簿・賃金台帳の確認 |
給与が支払われている期間は支給対象外 給与明細や出勤簿のコピーを添付するとスムーズ |
| STEP4:健康保険組合での審査 | – 申請から支給まで約1〜2か月 – 不備がある場合は再提出 – 初回支給後は継続申請が必要 |
支給まで時間がかかるため、生活費の見通しを 立てておくことが大切 再申請の際も同じ流れを繰り返す |
申請時の注意点とコツ
- 申請書類の記入漏れ
- 医師との連携不足
- 支給開始日の計算ミス
- 休職決定と同時に申請準備開始
- 会社の人事担当者との密な連携
- 医師への制度説明と協力依頼
私の場合、申請準備は行いましたが
人事担当者から「会社制度の方が有利」と
アドバイスをもらい、結果的に手続きが簡素化されました。
休職中の家計管理と節約術
支出の見直しポイント
固定費の削減
□ スマホ料金プランの変更 □ 保険料の見直し
□ サブスクリプション整理 □ 光熱費の節約対策
変動費の管理
□ 食費の予算設定 □ 交通費の削減
□ 娯楽費の調整 □ 医療費の家計簿管理
実際に効果的だった節約方法
通信費削減
- 格安SIMへの乗り換え:月3,000円削減
- Wi-Fi環境の見直し:月1,000円削減
食費管理
- 作り置き料理の活用
- 業務用スーパーの利用
- 冷凍食品の戦略的購入
医療費対策
- ジェネリック医薬品の選択
- 自立支援医療制度の活用
- 医療費控除の準備
減収でも、支出見直しにより、実質的な影響を
10万円程度に抑えることができました。
| カテゴリ | 見直しポイント | メモ |
|---|---|---|
| 固定費 | スマホ料金プラン、保険料、光熱費、サブスク | 年単位で見直すと効果大 |
| 変動費 | 食費、交通費、娯楽費、日用品 | 月ごとに予算を設定 |
| 医療費 | ジェネリック薬、医療費控除、自立支援医療 | 医療費レシートを保管 |
| その他 | 銀行・クレジットカードの手数料、不要サービス解約 | 1回の見直しで数千円削減可能 |
復職後の収入回復計画
段階的復職と収入の変化
復職パターン例
- 週3日勤務(給与50%)
- 週4日勤務(給与75%)
- フルタイム復帰(給与100%)
収入シミュレーション
- 復職1ヶ月目:17.5万円(50%)
- 復職2ヶ月目:26.25万円(75%)
- 復職3ヶ月目:35万円(100%)
復職ステージ 勤務日数 給与支給割合 想定月収(例:月収35万円の場合) 段階1 週3日 約50% 約17.5万円 段階2 週4日 約75% 約26.25万円 段階3 週5日(フルタイム) 100% 約35万円
復職準備中の経済計画
必要な準備資金
- 通勤用の衣類購入
- 交通費の月定期購入
- 昼食代の予算確保
- 歓送迎会等の交際費
収入安定化の戦略
- 副業・フリーランス収入の検討
▶ 初めて会社を辞めて独立を考えました - スキルアップによる昇進・転職準備
▶ 休職中に継続したオンライン英会話がスキルアップに繋がりました - 投資による資産形成の再開
私の場合、復職後は
以前よりも効率的な働き方ができるようになり
結果的に年収がアップしました。
休職期間中に身につけたセルフケアスキルが
長期的な生産性向上につながったのです。
休職を決断する前の経済準備
最低限確保すべき資金
緊急資金の目安
- 生活費3-6ヶ月分の貯蓄
- 医療費・薬代の予備資金
- 復職準備資金
資金調達方法
- 定期預金の解約
- 生命保険の契約者貸付
- 家族からの一時借入
- 会社の従業員貸付制度
事前に確認すべき制度
□ 給与保障の有無と条件 □ 社会保険料の負担方法
□ 賞与・昇給への影響 □ 復職支援制度の内容
□ 加入している健康保険の種類 □ 傷病手当金の支給条件
□ 自立支援医療の申請資格 □ 障害者手帳取得の可能性
よくある質問と回答
Q1:会社を辞めても傷病手当金は受けられますか?
A:退職日まで、継続して1年以上の被保険者期間があり
退職時に傷病手当金を受給中または受給条件を満たしていれば
退職後も引き続き受給可能です。
Q2:傷病手当金と失業保険は同時に受けられますか?
A:同時受給はできません。ただし、傷病手当金受給中は
失業保険の受給期間延長申請が可能です。
Q3:休職中にアルバイトはできますか?
A:就労不能状態での休職中は原則不可。
ただし、復職準備としての軽微な就労は
医師・会社と相談の上で可能な場合があります。
まとめ:経済的安心感が回復を促進する
重要ポイントの整理
- 会社制度:最も手続きが簡単で安定的
- 公的支援:傷病手当金を中心とした社会保障
- 民間保険:就業不能保険等の活用
私の実例
- 休職前収入:35万円/月
- 休職中収入:21万円/月(会社制度60%)
- 支出削減:4万円/月
- 実質影響:10万円/月の収入減
成功要因
- 事前の制度理解と準備
- 会社との良好な関係維持
- 計画的な家計管理
休職は「経済的な破綻」ではありません。
適切な制度活用により、安心して
治療に専念できる環境を作ることが可能です。
お金の心配を最小限に抑えることで
本来の目的である、心身の回復に集中できます。
制度を理解し、準備を整えて、安心して
治療の第一歩を踏み出してください。
現在休職を検討している方も、すでに休職中の方も
この記事が、経済的な不安軽減の一助となれば幸いです。
一人で抱え込まず
使える制度はしっかりと活用していきましょう。
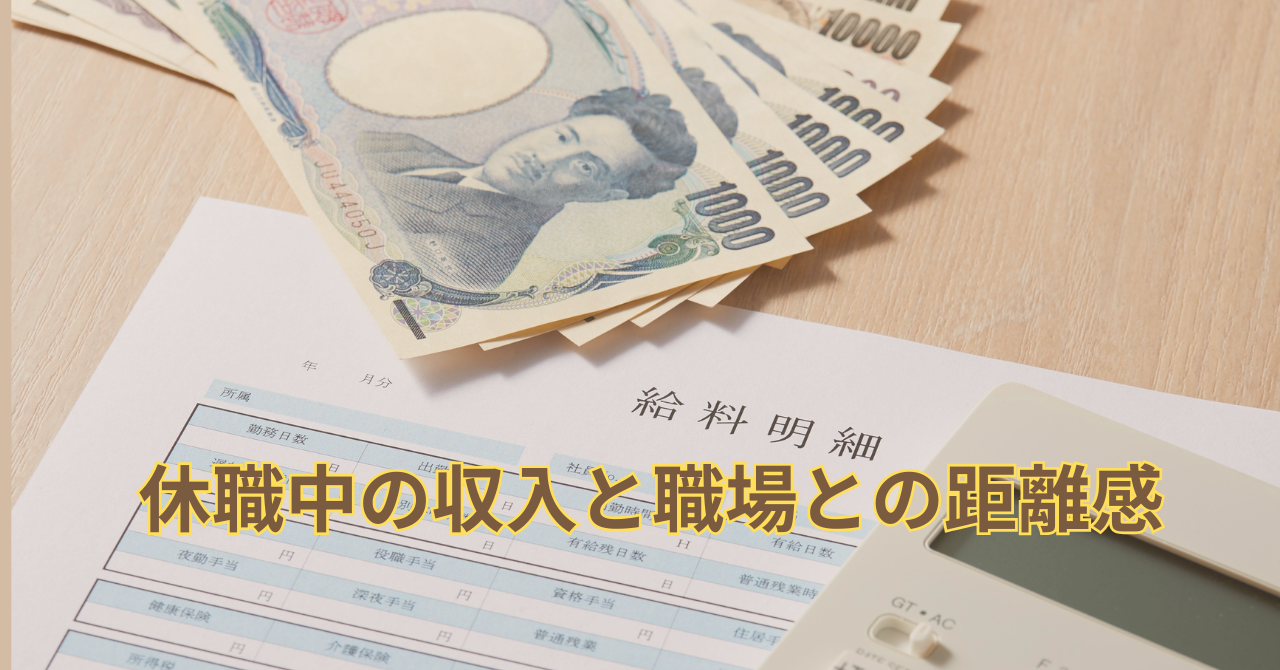
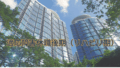

コメント