復職初日の朝、心臓がドキドキして足が重く、一歩がなかなか出ませんでした。
私自身、適応障害で休職していたとき、職場に戻ることが怖くてたまらなかったのです。
でも、それは「また仕事に向き合おう」という意欲の表れでもあります。
出社の途中、何度も「やっぱり無理かも」と思いました。
それでも、「今日を無事に終えることだけを目標にしよう」と心の中でつぶやき、少しずつ気持ちを落ち着けました。
同じように緊張している方へ伝えたいのは、初日は再出発の日であって、完璧にこなす日ではないということ。
小さな一歩で十分です。緊張していても構いません。
大切なのは、「戻る」という行動を選んだこと自体なのです。
- 復職初日の不安を和らげる心構え
- 出社前にできるメンタル調整と服装準備
- 初日のスケジュール例と人事面談の質問対応
- 上司・同僚への挨拶例文と手土産の選び方
- 緊張を和らげるための実践的工夫
- 初日を終えた後のセルフケア
- (体験談)私自身の気づき
【準備編】初日を安心して迎えるためのポイント
ここでは、「自分の心を整える準備」に焦点を当てます。
| 目的 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 自信をつける | お気に入りの一着を選び、「これで大丈夫」と鏡の前で自分に声をかける | 清潔感+自己肯定感を高める効果 |
| 段取りを整える | 前日夜に、朝の行動リストをメモしておく。「起きる→朝食→深呼吸→出発」と具体的に | 翌朝の迷いを減らし、安心して出発できる |
| 心を落ち着ける | 深呼吸法「4-4-8法」(4秒吸う→4秒止める→8秒吐く)を3回繰り返す | 自律神経が整い、緊張を緩和できる |
準備とは、服や物だけでなく「心を整えること」。
前日から「明日の自分を応援する」気持ちを作ることが、何よりの準備になります。
▶復職直前の不安との向き合い方|心を整える当日までの過ごし方
【心理ケア編】不安を和らげる3つの方法
復職初日は、誰にとっても緊張するものです。
その中で、私が助けられた気持ちの整え方を3つ紹介します。
- 深呼吸+肩回し:呼吸を整えながら、肩をゆっくり回すと体の緊張がほどけます。
- ポジティブワードを唱える:「完璧じゃなくていい」「一歩ずつでいい」と自分に言い聞かせる。
- 聴く姿勢を意識する:初日は話すよりも、相手の言葉を聞くことで安心感が生まれます。
復職初日の目的は信頼を取り戻すことではなく、自分を取り戻すことです。
焦らず、一歩ずつ慣れていけば大丈夫です
朝のセルフチェック
- 睡眠:就寝・起床時刻/中途覚醒は?
- 身体:動悸・息苦しさ・食欲は?
- 思考:完璧主義になっていない?
【実践編】復職初日の過ごし方と挨拶のコツ
復職初日の流れは、おおむね以下のようなスケジュールになります。
| 時間 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 9:00 | 人事・上司と面談 | 「無理せず徐々に慣らしていきたい」と伝える |
| 9:30 | 職場での挨拶 | まずは上司、その後チームへ |
| 10:00〜12:00 | 軽作業や環境確認 | 焦らず、流れを掴むことを意識 |
挨拶の内容は難しく考えすぎなくて大丈夫です。
大切なのは、感謝と前向きな意欲を伝えること。

挨拶例文:
「おはようございます。本日から復職いたします○○です。長らくお休みをいただき、ご迷惑をおかけしました。少しずつ慣らしていければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。」
声が震えても構いません。相手はあなたの頑張ろうとしている姿を見ています。
完璧な言葉より、誠実さと笑顔のほうが印象に残ります。
場面別の挨拶例文
上司への挨拶
「○○部長、お忙しい中ありがとうございます。本日から復職させていただきました○○です。ご迷惑をおかけしましたが、今後ともご指導よろしくお願いします。」
同僚への挨拶
「おはようございます。本日から復職いたします○○です。ご一緒できて嬉しいです。よろしくお願いします。」
新しいメンバーへの挨拶
「初めまして、○○と申します。本日から復職いたしました。至らない点もあると思いますが、よろしくお願いします。」
私が実際に伝えた挨拶と周囲の反応は体験記事にまとめています。
【体験談】職場復職初日の様子と心境
人事面談で想定される質問と答え方
Q:体調はいかがですか?
A:「おかげさまで安定しています。主治医から復職の許可をいただいております。」
Q:不安なことはありますか?
A:「緊張はしていますが、段階的に慣れていきたいと思います。」
Q:サポートが必要なことはありますか?
A:「ありがとうございます。必要な時は相談させてください。」
挨拶と菓子折りのマナー

誰に渡す?順番とタイミング
- 直属の上司
- 人事(お世話になった担当者)
- 同じチームのメンバー
おすすめの品物と目安
| 人数目安 | 予算 | おすすめ菓子例 | 日持ち | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 5〜10人 | 1,000〜1,500円 | 個包装クッキー・フィナンシェ | 約2〜3週間 | 少人数部署向け。配りやすい |
| 10〜20人 | 2,000〜3,000円 | 焼き菓子詰合せ | 約3〜4週間 | 迷ったら定番の詰合せでOK |
| 20人以上 | 3,000〜5,000円 | 小分けせんべい・個包装チョコ | 約1〜2か月 | 大人数向け。日持ち重視 |
「個包装/日持ち/アレルギー表示」。
この3条件を満たせば、まず失敗しません。
▶ 復職初日の菓子折り完全ガイド|適応障害から職場復帰した私の実践記録
まとめ 復職初日は完璧より一歩前へ

復職初日は、誰にとっても不安でいっぱいの日です。
でも、今日という日を迎えたあなたは、すでに大きな一歩を踏み出しています。
「緊張する自分を責めず、よくここまで来た」と声をかけてあげてください。
初日の結果よりも、戻る決意を持ったことが一番の成果です。
焦らず、少しずつ、自分のペースで。
完璧を目指すより、一歩前へ。
その積み重ねが、必ず復職を成功へ導きます。
復職・適応障害に関する関連記事はこちら
適応障害で休職・復職を経験した筆者が、うつなど心の不調を抱える方にも役立つよう、体験をもとにまとめています。
一歩ずつ、自分のペースで回復していきましょう。
関連記事(内部リンク)
出典
- 厚生労働省「職場復帰支援プログラム」
- 日本産業衛生学会「復職支援ガイドライン」
※本記事は筆者の体験と公開情報をもとに構成しています。医療的・法的助言を目的としたものではありません。個別の判断は、主治医・産業医・専門家にご相談ください。
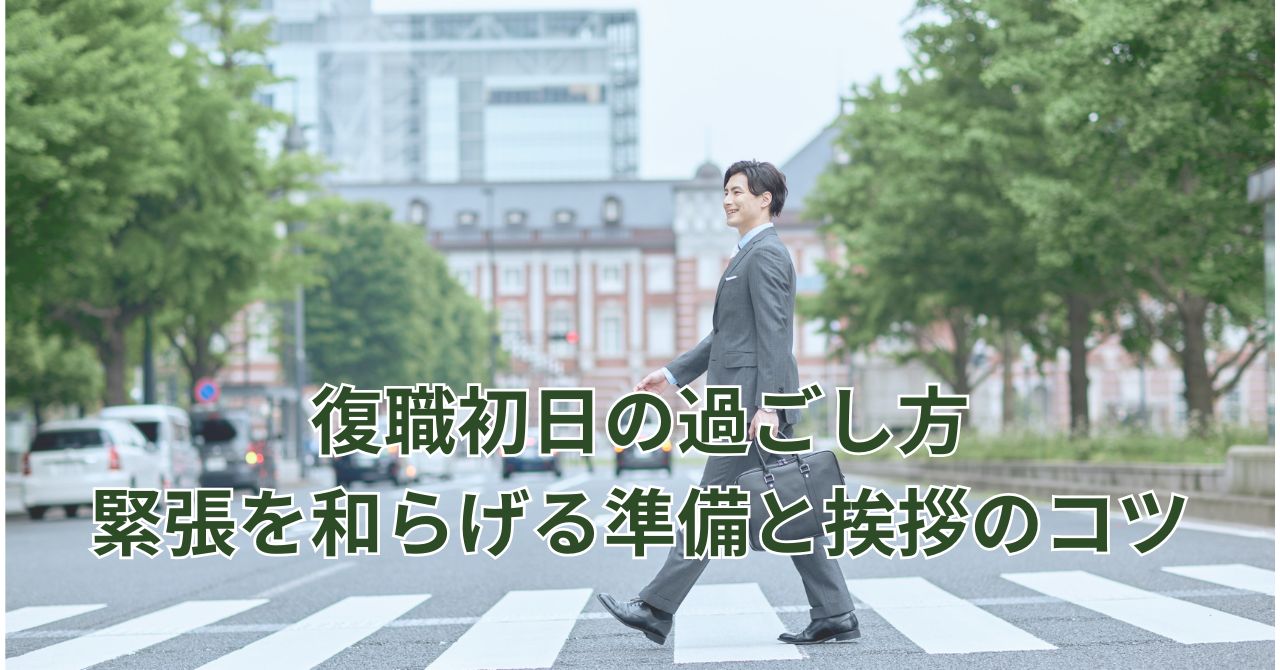


コメント