休職は決まったものの
「どう過ごせばいいかわからない」
「罪悪感で苦しい」
「このまま治らないのでは」
と不安を抱えていませんか?
私も、全く同じ気持ちでした。
元中間管理職として、適応障害で休職した私が、実際に経験した休職初期の現実と少しずつ、心が軽くなった具体的な方法をお伝えします。
「休む=何もしない」ができない理由から、自分らしく回復するための現実的なアプローチまで。同じ状況で苦しんでいる方の参考になれば幸いです。
🌱 復職・適応障害に関する関連記事はこちら
適応障害で休職・復職を経験した筆者が、うつなど心の不調を抱える方にも役立つよう、体験をもとにまとめています。
一歩ずつ、自分のペースで回復していきましょう。
休職初期に直面する現実:「完全に休む」ことの困難さ
理想と現実のギャップが生む心理的負担
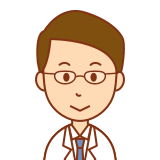
心身を休めることが最優先
医師や周囲の人は、必ずこう言います。しかし、現実は全く違います。
実際に休職してみると、何もしない=不安や罪悪感を感じるという状況に陥る人がほとんどです。
私自身も「このまま治らなかったらどうしよう」という強い不安に襲われ、家族への罪悪感を抱えながら日々を過ごしていました。
厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」でも、休職初期は、十分な休息をとり、治療に専念することが推奨されています。
しかし、この「十分な休息」が、責任感の強いビジネスパーソンにとって最も困難なことなのです。
中間管理職特有の責任感が引き起こす罪悪感
特に、中間管理職を経験してきた方は、以下のような感情に悩まされがちです。
- 部下への責任感:「チームに迷惑をかけている」という思い
- 成果主義の価値観:「何も生産しない自分への嫌悪感」
- 家計を支える立場:経済的プレッシャーと配偶者への申し訳なさ
これらの感情は、適応障害の症状を悪化させる要因にもなります。
産業保健・職場復帰支援の分野では、管理職など責任の大きい立場の人ほど、休職期間が長くなる傾向にあるという報告があります。
実際私も、職責の重さによるプレッシャーが、回復をじわじわ遅らせたように感じました。
私が休職直後に感じた3つの感情【体験談】
家族への申し訪なさが最も重い負担だった
休職初期に私を最も苦しめたのは、次の3つの感情でした。
1. 家族への強い罪悪感
- 経済的な不安を与えていることへの申し訳なさ
- 支えてもらうことへの情けなさ
- 「家族のために頑張らなければ」というプレッシャー
2. 将来への漠然とした不安
- 「このまま治らないのでは」という恐怖
- 復職できるかわからない焦り
- キャリアの中断に対する危機感
3. 時間への焦燥感
- 「早く治さなければ」という圧迫
- 何もしない時間に対するイライラ
- 「時間を無駄にしている」という強迫観念
興味深いことに、会社に対する罪悪感は意外に少なく、家族への負担感が、心を最も重くしました。
これは、私たちが本当に大切にしているものが何かを教えてくれる体験でもありました。
将来への不安と時間への焦燥感
特に、40代以上の管理職にとって、休職は「キャリアの終わり」を意味するのではないかという不安が強くなります。
管理職としての復職は、責任の重さや職場での立場ゆえに、一般職よりもプレッシャーを感じやすいと言われています。
それでも、適切な支援や環境調整があれば、安定した復帰は十分に可能です。
実際、企業の産業保健分野の研究では、復職支援プログラムを導入した場合、復職後1年の出社継続率が約54%から91%に改善したという報告もあります。
(出典:難波ほか「メンタルヘルス不調者の復職支援プログラム効果」日本産業衛生学会誌)
この結果からもわかるように、早い段階で職場や産業医と連携しサポート体制を整えることが、元の職位での復帰や、より良い形での再スタートにつながっていきます。
▶ 中間管理職の責任と評価のギャップ|報われない働き方について
なぜ「何もしない」が困難なのか:働く人の心理的メカニズム
労働を美徳とする価値観の呪縛
ブログやSNSでは「休職直後は何もしないでいい」とよく書かれています。
しかし実際には、以下の心理的要因で「何もしない」こと自体が、大きなストレスとなります。
・労働を美徳とする価値観:何もしない=怠けていると感じる
・生産性への固執:成果を出さない時間への耐性の低さ
・社会的責任感:他の人が働いている間の罪悪感
頭では「休むのも仕事」と理解していても、心はそれを受け入れることができませんでした。
生産性への固執が生む自己嫌悪
現代のビジネス環境では「タイムマネジメント」「効率化」「成果主義」が重視されます。
こうした環境で長年働いてきた人にとって「生産性のない時間」は耐え難い苦痛となります。
しかし、心理学や脳科学の分野では、何もしない時間が、脳の回復や心の整理に役立つ
ことが分かっています。
この現実を受け入れることから、真の回復が始まります。
実際の過ごし方:私の1ヶ月間の詳細記録と学び
第1週:混乱期「何をしていいかわからない」
| 曜日 | 時間帯 | 行動・出来事 | 気持ち・気づき |
|---|---|---|---|
| 月曜日(休職初日) | 6:30 | いつものアラームで起床 | 出社しないことへの強い違和感 |
| 8:00 | 普段の3倍の家事をこなす | 罪悪感を紛らわせようと無理に動く | |
| 10:00〜15:00 | テレビをつけてもぼーっとする | 何も頭に入らず虚無感 | |
| 15:00 | 仕事のメールを確認 | すぐ後悔し、気持ちが沈む | |
| 夜 | 何も生産しなかったと自己嫌悪 | 「自分は役立たずだ」と感じる | |
| 火・水曜日 | 朝 | 6時に自然に目が覚める | 体が仕事モードから抜けられない |
| 昼間 | 時間が異常に長く感じる | 一日が終わらず焦りと不安 | |
| 終日 | 外出できない | 近所の目が気になり引きこもる | |
| 木・金曜日 | 朝 | 初めて8時まで眠れた | 少しずつ体が休息モードに切り替わる |
| 日中 | 家族に「大丈夫?」と聞かれる | 安心と同時にプレッシャーを感じる | |
| 夕方 | 10分だけベランダに出る | 小さな一歩に達成感 |
第2週:受容期「これが現実なのか」
この週に起きた具体的な変化:
| 日付 | できたこと | 気づき |
|---|---|---|
| 月曜 | 朝9時まで睡眠 | 「体が本当に疲れていた」初めての実感 |
| 火曜 | 洗濯物を干せた | 小さな家事にほっとする自分を発見 |
| 水曜 | 近所のコンビニに行けた | 5分の外出が大きな一歩に感じた |
| 木曜 | 家族と30分会話 | 久しぶりに笑うことができた |
| 金曜 | 鳥のさえずりに気づく | 外の世界を意識できるように |
2週目の終わりに起きた転機:
家族から「頑張って治そうとしなくていいよ」と言われた瞬間、涙が止まりませんでした。それまで我慢していた感情が溢れ出したのです。
第3-4週:安定期「自分なりの休み方を見つける」
最低限のルーティンが固まった時期:
| 時間帯 | 活動内容 | 気持ちの変化 | 所要時間 |
|---|---|---|---|
| 朝7-8時 | 起床、コーヒータイム | 「今日も休んでいい」と自分に言い聞かせ | 30分 |
| 9-10時 | ベランダで日光浴 | 体内時計が少しずつ整ってきた | 10-15分 |
| 11-12時 | 軽い家事(洗濯等) | 「これだけでも十分」と思えるように | 15-30分 |
| 午後 | 動画・読書・昼寝 | 罪悪感が薄れ、心から休めるように | 2-3時間 |
| 夕方 | その日の「できたこと」を1つ見つける | 自己肯定感の回復を実感 | 5分 |
| 夜 | 家族との時間 | 支えられていることへの感謝 | 随時 |
3週目の大きな気づき:
「完全に何もしない」ことに、こだわるのをやめ「自分らしく休む」ことを目標にした瞬間から、心が軽くなりました。
第4週:回復の兆し「小さな変化への気づき」
4週間目に初めて感じられた変化:
- 朝のコーヒーが美味しく感じられた(味覚の回復)
- 好きな音楽をかけることができた(感情の回復)
- 「明日は散歩してみようか」と思えた(意欲の萌芽)
- 家族の笑い声に自然に反応できた(社会性の回復)
1ヶ月経過時点での日記の一文:
「まだ先は見えないけれど、少しずつ『自分』を取り戻している気がする。」
完全な引きこもりから得られた重要な学び
この過ごし方が私に合っていた理由:
・「何もしない」よりも小さな達成感を得られた「洗濯物を干せた」だけでも自分を褒められるように
・外部からの刺激を最小限にできた SNSや仕事関連の情報を遮断することで心が安定
・自分のペースで回復段階を進められた 他人と比較せず昨日の自分より少しでも良い状態を目指す
・家族との関係性を見つめ直せた 支えられることの有り難さを実感し感謝を言葉で表現
これは「段階的な回復プロセス」の理想的な進行だったと理解しています。
焦らず、完璧を求めず、自分のペースを尊重することが、長期的な回復の基盤となりました。
心が楽になった7つの具体的な工夫【実践編】
認知の転換:「休むのも治療」を体に染み込ませる
少しずつ気持ちが軽くなった考え方の転換をご紹介します。
思考パターンの変更:
- 「休むのも治療の一部」と毎朝鏡を見ながら自分に言い聞かせる
- 「今日はこれで十分」と小さな行動も認める習慣をつける
- 回復は直線的でないことを受け入れ、波があって当然と考える
- 完璧に休むのではなく、自分らしく休むことを目標にする
小さな行動の積み重ねで達成感を育む
日常の具体的な工夫:
1. 感謝の表現で関係性を安定させる
家族への感謝を、毎日1回は言葉で表現 支えてもらう安心感を意識的に育む
2. 自然との接触でリフレッシュ効果を得る
窓から光を浴びるだけでも気分転換になる ベランダで3分間外の空気を吸う
3. 小さな成功体験を積み重ねる
「今日できたこと」に注目する習慣 「洗濯物を干せた」「30分散歩できた」など、どんな小さなことでも自分を褒める
4. 情報の断捨離でストレスを軽減
SNSや仕事関連の情報を意識的に遮断 ネガティブなニュースは避け、心地よいコンテンツのみ選択
休職初期のやることリスト・やらないことリスト
今日からできる3つの小さな行動
【やることリスト】
| 行動 | 目的 | 目安時間 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 朝の日光浴・軽い散歩 | 体内時計の調整、不安軽減 | 5-15分 | ベランダで5分間日光を浴びる |
| 「できたこと」を1行記録 | 小さな達成感の積み重ね | 1-3分 | 「今日は洗い物をした」と手帳に書く |
| 家族への現状共有 | 罪悪感の軽減、支援要請 | 週1回 | 「不安だけど休む練習中」と伝える |
避けるべき5つの行動パターン
【やらないことリスト】
| 避ける行動 | 理由 | 期間 |
|---|---|---|
| 将来の重要な判断(退職・転職の結論) | 不安状態での判断は適切でない | 初期1-2ヶ月は保留 |
| SNSや仕事チャットの常時チェック | 刺激や比較によるストレス増加 | 通知は完全にOFF |
| 「早く治さなければ」という焦り | かえって回復を遅らせる | 回復期間中は避ける |
| 完璧主義的な休息の強要 | 「何もしない」へのプレッシャー | 自分のペースを重視 |
| 他人との過度な比較 | 自己否定感の増大 | 情報収集は最小限に |
まとめ:あなたの責任感は回復後の強みになる
あなたの感じている気持ちは正常な反応です
「うまく休めない」と感じているなら、それはあなたが、責任感の強い優秀な社員だった証拠です。その責任感が今は重荷になっていますが、回復後は必ずあなたの強みとなります。
休職初期の過ごし方:重要ポイント
・完全に「何もしない」にこだわらない
・罪悪感や不安は正常な反応として受け入れる
・最低限から始めて小さな達成感を積み重ねる
・「休むのも治療」という認識を何度も確認する
・今日できたことを1つ見つけて自分を褒める
・「休むのも仕事」と声に出して言ってみる
・支えてくれる人に「ありがとう」を伝える
休職初期は「うまく休めない」と感じる人がほとんどです。
それでも大丈夫。小さな行動を認め、自分なりのペースで進んでいくことが確実な回復への道筋となります。
あなたは、一人ではありません。
時間をかけて、着実に前進していきましょう。
関連記事
休職前の段階で気づける症状について
▶適応障害の初期症状をセルフチェック
休職から復職への具体的なステップ
▶復職前に準備すべきチェックリスト【体験談付き】
復職後の予防策として
▶中間管理職のストレス対策:部下と上司に挟まれた時の心構え
※本記事は筆者の体験と公的情報(厚労省・自治体資料など)をもとに構成しています。
医療的な判断や治療方針については、主治医・産業医などの専門家にご相談ください。

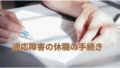

コメント