「休んでいるだけで本当に回復するのだろうか」
「休職中、何をすればいいのかわからない」
休職中期を迎えたあなたは、そんな気持ちを抱えていませんか?
私も当時、全く同じ思いを経験しました。
適応障害で休職し、何もできない状態から少し抜け出すと、今度は「このままでいいのか」という新たな不安が生まれます。
でも、安心してください。
この記事では、中間管理職として勤務した私が、休職中期の具体的な過ごし方と小さな行動がもたらした大きな変化について実体験をもとにお伝えします。
この時期の過ごし方が、その後の働き方と人生を大きく左右する重要な局面なのです。
休職中期とは:仕事を見直す転換点
適応障害の回復段階における中期の特徴
適応障害休職中期(回復期)の過ごし方は、単純に「休むだけ」の時期から、一歩進んだ段階です。
厚生労働省の「心の健康づくり指針」などによると、メンタル不調からの回復は段階的に進めることが大切とされています。
休職中期には、少しずつ外出への意欲が戻ったり「何かしたい」という気持ちが芽生えたりする時期です。
短時間なら集中できるようになったり「働くことへの不安」「もう一度やってみたい」という気持ちが混ざることもあります。
大切なのは大きなことを始める必要はないということです。
診察や買い物といった短時間の外出から始めて、気分が乗れば、小さな挑戦に取り組む。
この積み重ねが、心に前向きなエネルギーを生み出します。
働き方を再設計する準備期間としての位置づけ
私は、この休職中期こそが、働き方を根本から見直すきっかけとなりました。
・自分の価値観と仕事の適合性
・ストレス要因となっていた業務や人間関係
・ワークライフバランスの理想と現実のギャップ
・今後のキャリアプランと働き方の選択肢
この時期は単なる休養ではなく、新しい働き方を模索する貴重な準備期間だと捉えることが重要です。
休職中期のリアルな過ごし方|私の1ヶ月の記録
生活リズムを作った定期的な流れ
私の場合、2週間から1ヶ月ごとの診察が生活の軸となりました。
基本的なルーティン:
- 心療内科での定期診察(月1〜2回)
- 診断書を会社に提出(郵送で対応)
- 人事部との最小限のやりとり
この定期的な流れが、生活にリズムを与え、少しずつ心の安定につながりました。診察のための外出が、最初のリハビリのような役割を果たしてくれたのです。
段階的に広がった外出範囲とセルフケア
休職初期は引きこもっていた私ですが、適応障害回復期である中期に入ると徐々に行動範囲が広がりました。
第1段階:必要最小限の外出
- 病院への通院(月2回程度)
- 近所で買い物(週1〜2回、短時間)
第2段階:少し余裕のある外出
- 図書館で本を借りる(静かな環境での軽い活動)
- 散歩を兼ねた買い物(30分程度の外出)
短い外出でも、外の空気を吸い、人と接することで確実に気分が変わりました。
無理に長時間出かける必要はありません。日常生活の中で小さな外出を積み重ねることが、最も効果的でした。
| 段階 | 外出内容 | 頻度・滞在時間の目安 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 第1段階 必要最小限の 外出 |
・病院への通院 ・近所で買い物 | 通院:月2回程度 買い物:週1〜2回、10〜20分 |
まずは必要な用事だけに絞る。 外出後は休息をしっかり取る |
| 第2段階 少し余裕のある外出 |
・図書館で本を借りる (静かな環境で過ごす) ・散歩を兼ねた買い物 |
30分程度の外出 | 無理せず「やりたい」と思える時だけ行動。 翌日は休息日を入れる |
「何かしないと」から始まったスキル向上への挑戦
オンライン英会話:コミュニケーション能力の復活
休職中期になると「ただ休んでいるだけでいいのか」という焦りが出てきます。この焦り自体は悪いものではありません。回復が進んでいる証拠です。
私も「何かやらなきゃ」という気持ちから、いくつかの新しいことを始めました。
最も効果的だったのが、オンライン英会話でした。
期待していた効果:英語力の向上、時間の有効活用
実際に得られた効果:孤独感の解消、コミュニケーション能力の回復
正直に言うと、英語の上達よりも「誰かと話せること」が一番の助けになりました。
毎日短時間でも、人との会話が孤独感を和らげ、気分を前向きにしてくれたのです。
▶ 休職中に支えになったオンライン英会話|8サービス体験して選んだおすすめ
▶ QQ English体験レビュー|8社比較で残った「心を整える」英会話
料理:創造性と達成感の回復
近所の方からいただく野菜が大量にあったことをきっかけに、簡単な料理を始めました。
料理がもたらした予想外の効果:
- 「食材をどう活かそうか」と考える時間が良い気分転換になった
- 完成した料理から小さな達成感を得られた
- 食生活が整い、体調改善にもつながった
- 将来の働き方(料理系副業)への可能性も見えた
料理は短時間で完結し、目に見える成果が得られる理想的な活動でした。
休職中期の制度活用と注意点
会社制度の効果的な活用法
休職中は経済的な不安も大きなストレス要因となります。私が実際に活用した制度をご紹介します。
活用した支援制度:
- 会社の福利厚生:定期面談、復職支援プログラム
- 地域の相談窓口:市町村の心の健康相談
手続きで学んだポイント:
- 診断書の提出は期限を厳守
- 人事担当者とは必要最小限のやりとりに留める
- 復職時期については医師と相談して慎重に判断
頑張りすぎを防ぐセルフモニタリング
この時期に最も重要なのは「無理をしないこと」です。
私が実践した「無理をしない」基準:
- 外出は短時間でもOK(15分でも十分な成果)
- 勉強や趣味は「できたらやる」程度の気持ちで
- 家事や料理は「やらなきゃ」ではなく「気が向いたら」
疲労感が以前より強くなった
不安や焦りが増している
睡眠の質が悪くなった
このような症状が出た場合は、すぐに活動量を調整することが重要です。
中間管理職経験者が教える復職への準備
「完璧主義」からの解放と働き方再構築
中間管理職時代の私は、常に完璧な成果を求めていました。
しかし、休職中期に学んだのは「60点の行動を継続することの価値」でした。
完璧主義から抜け出すための思考転換:
- 「100点を目指して0点」より「60点を継続して積み重ね」
- 「全てを一人でこなす」から「適度に人に頼る」働き方へ
- 「残業=努力」から「効率化=成果」への価値観転換
完璧を目指さず、継続可能な小さな行動を重ねることで確実に前進できるのです。
やらないことリスト|復職を妨げる行動の排除
休職中期では「やること」と同じくらい「やらないこと」を明確にすることが重要です。
| やらないこと | 理由・ポイント |
|---|---|
| 会社の同僚や上司との連絡(緊急時以外) | 余計なストレスや罪悪感を避け、回復に集中するため |
| SNSでの仕事関連情報の収集 | ネガティブ情報や他人の状況に引きずられやすい |
| 無理な外出や活動の強要 | 回復ペースを乱し、再び体調を崩すリスクがある |
| 他人との回復スピード比較 | 自分のペースを大切にするため。他人は参考程度に |
| 「早く復職しなければ」という焦りに振り回される | 回復は波があるもの。焦りは逆効果になりやすい |
これらを避けることで、回復に専念できる環境を整えることができます。
🌱 復職・適応障害に関する関連記事はこちら
適応障害で休職・復職を経験した筆者が、うつなど心の不調を抱える方にも役立つよう、体験をもとにまとめています。
一歩ずつ、自分のペースで回復していきましょう。
まとめ:今すぐ始められる3つのアクション
- 外出や小さな挑戦を通して、段階的に回復を進める
- 定期的な診察が、生活のリズムと安定をもたらす
- 短時間の外出から始めて、徐々に活動範囲を広げる
- プチ学習や料理など、小さな挑戦で気分が前向きになる
- 「無理をしない」「小さな達成感を積み重ねる」ことが最重要
明日から始められること
- 散歩や近所への買い物から外出を再開
- 何か一つ、興味のあることを始める
- できたことを1つ見つけて、自分を認める
希望のメッセージ
休職直後は何もできなくても、休職中期には、自然とできることが増えていきます。
その変化こそが、あなたの回復の確かな証拠なのです。
小さな一歩から始まる大きな変化を、私は身をもって経験しました。
現在、私は会社員として働きながら、心理やカウンセリングの学びを活かしライターとして発信を続けています。この休職経験が、新しい働き方への転換点となりました。
焦らず、でも着実に一歩ずつ前進していきましょう。
あなたは確実に、回復に向かっています。
【まとめ】適応障害からの休職と復職までの体験談|全記事まとめ
※本記事は筆者の体験と公的情報(厚労省・自治体資料など)をもとに構成しています。医療的な判断や治療方針については、主治医・産業医などの専門家にご相談ください。
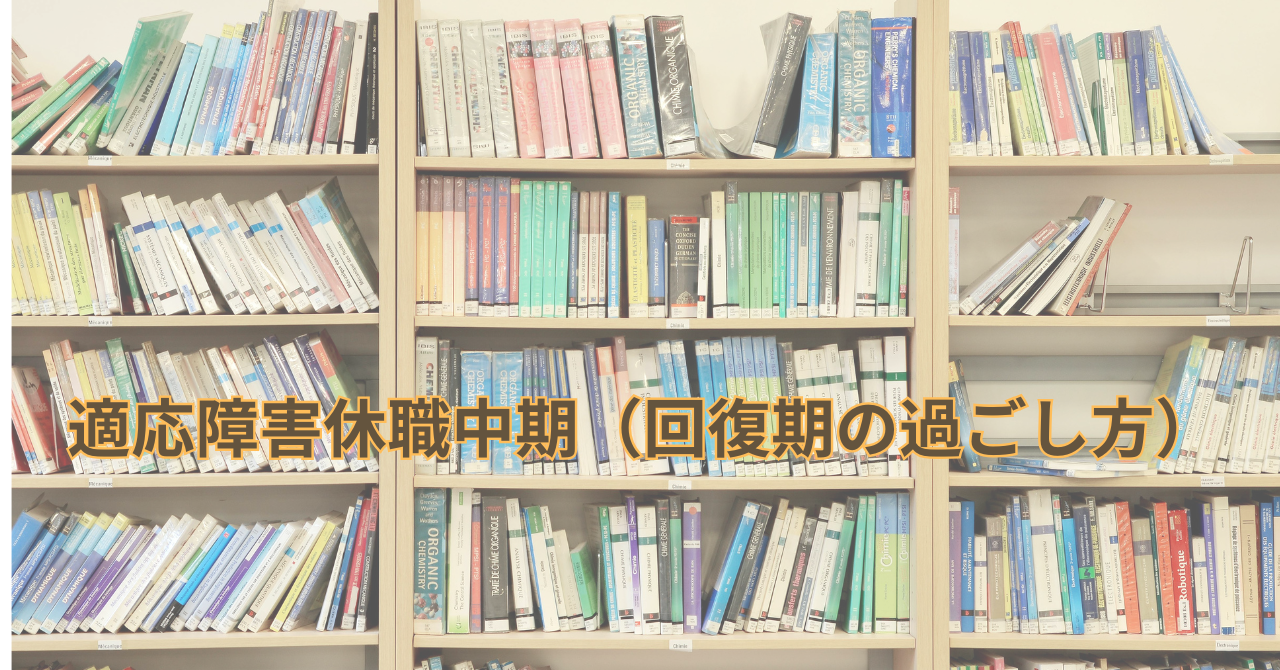

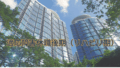
コメント